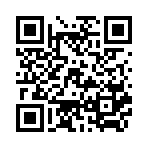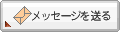ひとりごと
『琉球(沖縄)の長寿』を知る
『琉球(沖縄)の長寿』を知る
『琉球王国時代(沖縄)』の長寿法
1392年(琉球王国が樹立する37年も前のこと)、琉球国に
洪武帝の命により多くの学者や航海士などの職能集団が来琉したと言われています。
その人々は那覇の久米村 (現・那覇市久米、唐栄とも) に定住したことから
久米三十六姓と呼ばれ、琉球の文化(食)の発展に大きく寄与していたことはもとより
肥満抑制、痩身(ダイエット)、病気予防等にも貢献していたのです。
そしてそれらによって健康寿命を延ばし長寿社会を造っていました。
その職能集団は
文学、舞踊、音楽、工芸、武芸、経済学、言語学、宗教学、風水学及び健康学等の
エキスパートの集まりと考えます。
健康学の中に現代でいうところの食物学、薬学、気功、鍼灸、指圧及びマッサージ等の
エキスパートも含まれていたと考えます。
残念なことに一部の歴史学者にとって健康学、特にマッサージ等の文献は興味を引くことがなく
多くの文献が藻屑となってしまったのではないでしょうか。
長寿の基礎は『食』
琉球の食は、かなり完成されていて中国から伝来したものや琉球の長い歴史によって
蓄積された経験や統計によって実証されてきたものだったのです。
その中でも特に注目したいのは
① 十分な水分の摂取
② オイル(必須脂肪酸)の摂取
③ アクを摂らない調理(食事)
① 十分な水分の摂取
私の実家(那覇市内)は私が幼い頃、隣に祖父母と曾祖母が
住んでいていつでも行き来できる状態でした。
私の祖母も曾祖母も長寿で百歳くらいまで元気でした。
そして、母ももうじき94歳、なぜみんな長寿なのでしょうか。
私が幼いころよく目にしたのは、どこの家でもそうだったと思いますが
家に入るとそこにはちゃぶ台が有って急須とお茶碗とお茶入れとポットが
置いてありました。そして黒砂糖等も置いてありました。
私の祖父母と曾祖母はいつでもお茶を飲んでいてその手が止まることは
有りませんでした。3~4リットルは飲んでいたのではないでしょうか。
それに、食事の時に頂く味噌汁も欠かすことがなかったので
それも十分な水分摂取につながったと思います。
② オイル(必須脂肪酸オメガ3,6,9【ω‐3、ω‐6、ω‐9】)の摂取
琉球料理の代表的調理方法に、チャンプルーとイリチーが有ります。
近年その違いが分かっている人は少なくなってきています。
それではチャンプルーとイリチーの違いを考えてみましょう。
チャンプルー
チャンプルーの語源はちゃんぽんでこれは2種類以上のものを混ぜるという意味が有ります。
琉球料理には、本来生の食材を口にする習慣は有りませんでした。
野菜はアクが有るので必ず茹でてアク抜きをしていました。これは冷蔵庫がない時代に
新鮮な野菜が傷むのを防ぐためや保存の為でもありました。
ですから、すでに茹でられた野菜と豆腐や卵などに油(菜種油やごま油)を加えて、温めながら
混ぜ合わせた料理のことをいいます。
ごーやーチャンプルー、まーみなーチャンプルー、にんじん(ちでーくに)チャンプルー、
豆腐チャンプルーなどがある。にんじんの場合は調理器具の進化で細く加工することを
シリシリーということからにんじんシリシリーということが多いです。
イリチー
イリチーの語源は炒る、炒めるで、食材に火を通し水気が少なくなるまで
火を通しすという意味が有ります。
基本的には野菜以外のものを調理する時に使われます。
昆布もその一つで、乾燥昆布を水で戻し塩抜きをしてそうめんのような細切りにして
豚肉やこんにゃく等とともに油(菜種油やごま油)で炒めた料理のことをいいます。
クーブ(昆布)イリチー、中身イリチー(中身は汁ものした中身汁もあります)などがある。
ここで注目したいのは油(菜種油やごま油)で
『な なたね油』 には必須脂肪酸のなかの
オメガ3 と 6 が含有されていて
『ごま油』 には
オメガ6 と 9 が含有されています。
琉球王朝時代 (祖父母と曾祖母の時代) には油をしっかりと摂取するように
言い継がれていたと聞いています。
私が就職で内地に行く際にも、祖母から油をしっかり摂るようにと方言で言われました。
また、昆布は一人当たりの消費量が沖縄が日本一なのです。
昆布にはオメガ3の成分が多く含まれています。
現在のようにオメガ3,6,9という学名はなかったはずですが、長年の経験から
生まれてきた知恵が油の積極的な摂取なのです。
参考:味噌汁にも油がいっぱい入っていました。
油は味噌汁には必ず入れられていました。
料理研究家や料理教室の先生等が味噌汁のオイルは
具の野菜のために入れるとテレビで話されていましたが、
それは間違っていると思います。
具のない味噌汁にも油はいっぱい入っていました。
また一般的な味噌汁は、具だくさんで、実家ではいろいろな野菜と豆腐それに
昆布が多く使われていました。私が好んで食べていたのは玉ねぎの味噌汁で、
玉ねぎの甘みが最大限に生かされていました。
味噌汁を作るときに重要なポイント。
㋑ 具の野菜のアクをしっかり取り除くこと
(野菜のアクは、寿命を縮めるばかりではなく、
アレルギーやアトピーを引き起こしたり、肌のトラブルの原因にもなります。)
㋺ 味噌は火を止めてから入れること、味噌を入れた後は煮立足さないこと。
(味噌は発酵食品ですので、菌が死んでしまわないようにするため。)
㋩ 塩や砂糖等の調味料は控えめにすること
(琉球でいうところのあじくーたーは味が濃いことでは有りません具になる
野菜等のうまみを引き出したコクのある美味しさのことを言うのです。)
③ アクを摂らない調理(食事)
『アク』 って何なんでしょう。
アクは簡単に言うと毒素です。すべての食材には何らかのアクが有ると言っても
過言では有りません。アクは身体の調子を崩したりする原因でもあります。
セルライトはアクや毒素が動物性脂肪と一緒になることによってできます。
ですから、生野菜を摂り続けると、いつの間にかセルライトが増えてしまいます。
スムージーやコールドプレスジュースも同じで撮り続けるとセルライト工業が増えます。
しかも、身体(肉質)が硬くなったりすることと、セルライトそのもので気の流れやリンパの
流れも悪くなってしまいます。
また、一般的には身体を冷やしてしまうので基礎体温の低下を招いたり、冷え性に
成り易くなります。
南国生まれの野菜は身体を冷やす働きをし、北国生まれの野菜は身体を保温する
働きをします。
ゴーヤーは夏野菜で夏の暑さを和らげる働きをします。
参考:スムージーもコールドプレスジュースもアメリカで流行し、
日本でも流行しているようですが、アメリカは世界NO1 或は NO2位の肥満国なのです。
しかも、年齢を重ねるほど肌がボコボコになっているということも知って下さい。
近年、アメリカと肥満世界NO1位、2位を争っているのがメキシコです。
メキシコはアメリカの企業の宣伝を観て、アメリカのダイエット製品を買っています。
それが肥満大国という不名誉な結果を生んだのです。
琉球では徹底してアク抜きをしていました。
野菜は勿論、豚肉も煮込んでアクを抜いていました。
また、パイナップルなどのアクの強い果物もアク抜きをしていました。
パイナップルは、食べると口の中がピリピリします。
それはパイナップルのアクの作用によります。
私の母や祖母もパイナップルのアク抜きをしていました。
アク抜きされたパイナップルはとても美味しいので
お腹いっぱい食べていた記憶が有ります。
(パイナップルのアク抜き法はまた別の機会に)
(記述途中)
『琉球王国』
琉球王国(りゅうきゅうおうこく)は、1429年から1879年の450年間、
沖縄本島を中心に存在した王国。当時、正式には琉球國(りゅうきゅうこく、
琉球語(琉球方言):ルーチュークク)と称した。
最盛期には奄美群島と沖縄諸島及び先島諸島までを統治した。
この範囲の島々の総称として、琉球列島(琉球弧)ともいう。王家の
紋章は左三巴紋で「左御紋(ひだりごもん、フィジャイグムン)」と呼ばれた。
勢力圏は小さな離島の集合で、総人口17万に満たない小さな王国では
あったが、隣接する大国 明・清の海禁や日本の鎖国政策の間にあって、
東シナ海の地の利を生かした中継貿易で大きな役割を果たした。
その交易範囲は東南アジアまで広がり、特にマラッカ王国との
深い結び付きが知られる。
外交的に貿易上の理由から、明及びその領土を継承した清の冊封を
受けたりしていたが、1609年に日本の薩摩藩の侵攻を受けて以後は、
薩摩藩による実質的な支配下に入った。ただし対外的には独立した王国
として存在し、中国大陸、日本の文化の影響を受けつつ、交易で流入する
南方文化の影響も受けた独自の文化を築き上げた。
(Wikipediaより抜粋)
『久米三十六姓』
久米三十六姓(くめさんじゅうろくせい)は、1392年に明の洪武帝より琉球王国に
下賜されたとされる閩人(現・福建省の中国人)の職能集団、及びその後三百年間にわたり
閩から渡来した者や首里・那覇士族から迎え入れた人々の総称。
(Wikipediaより抜粋)
(記述途中)






運気を上げる器 (こつこつ集めた器)
ロイヤルクラウンダービー
ヘレンド (ビクトリアシリーズ)
リチャードジノリ (イタリアンフルーツ)
オオクラ
ノリタケ
ノリタケ
ウェッジウッド
紅茶 (ウェッジウッド・プッカ・リプトン・日東) と ティーカップ